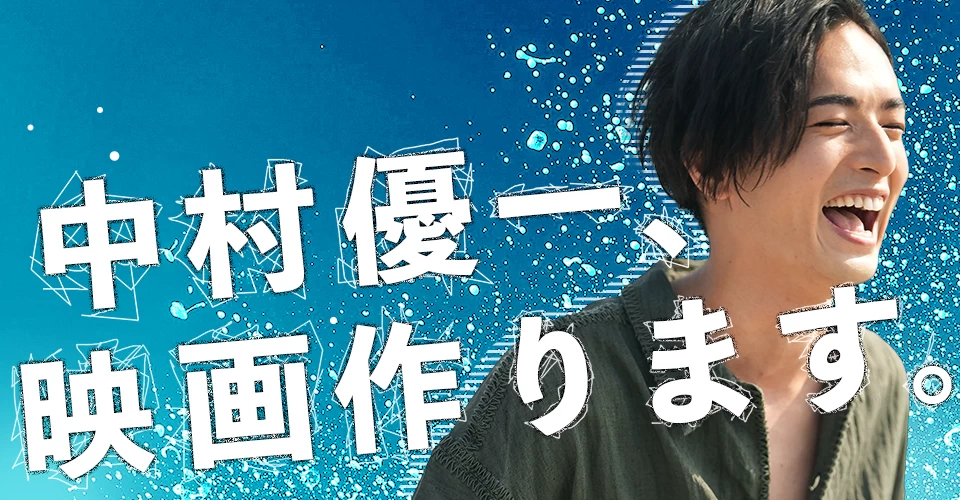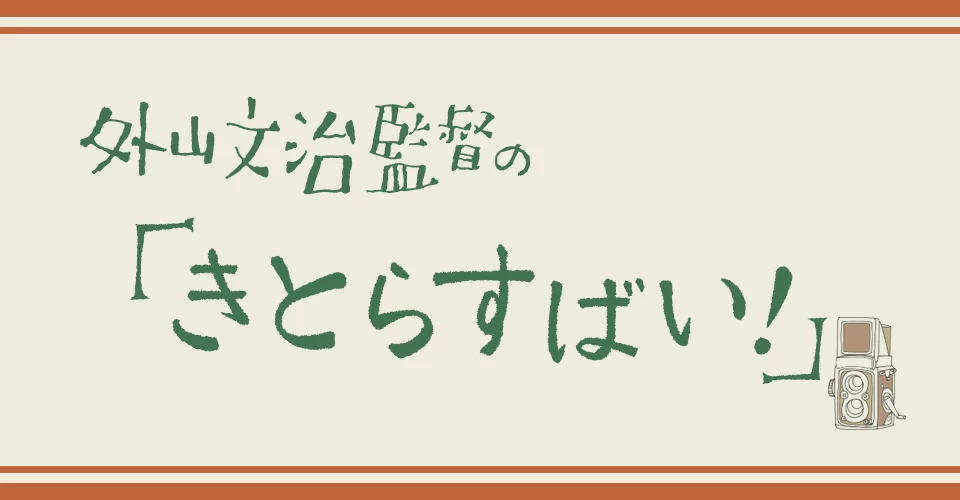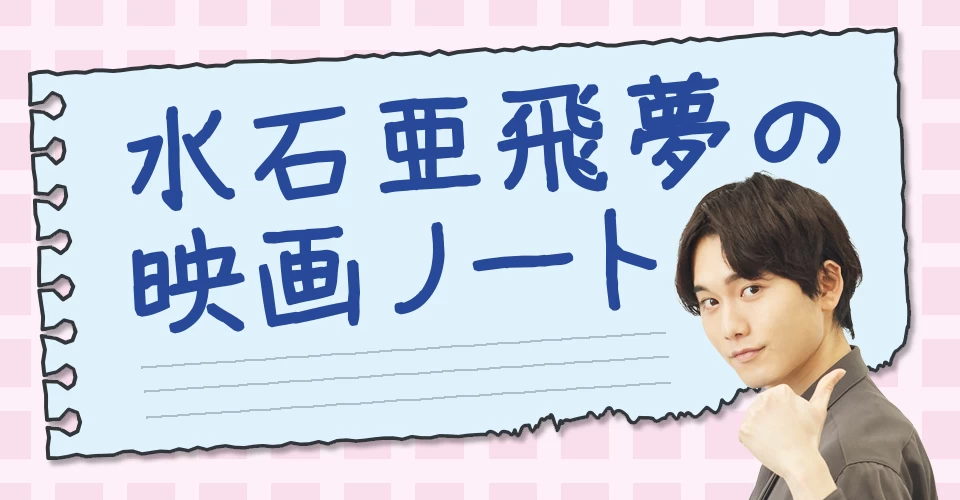岡山天音「その人にしかないまったく違う人生に思いを馳せることが大切」 『笑いのカイブツ』インタビュー 2024.1.5


岡山天音を主演に迎え、滝本憲吾監督が長編商業デビューを果たした『笑いのカイブツ』。ツチヤタカユキによる同名私小説を原作に、“伝説のハガキ職人”と呼ばれた男の半生を描いた作品だ。観る者すべてを圧倒する深度でツチヤの半生を体現した岡山は、自分が無くなるほど削られたのだという。実在の人物を演じることや、役と自身の共通点などについて語ってもらった。
原作者・ツチヤタカユキとの特殊な関係性

──本作への出演の経緯を教えてください。
岡山「オファーをいただいて、まず原作を手に取りました。もともとツチヤさんのことは知っていましたし、彼の関わったラジオ番組も聴いていたのですが、原作は読んだことがなかったんです。原作に登場するツチヤタカユキはマグマのようなキャラクターで、その形容し難い魅力に惹かれて出演することになりました」
──実在するかたを演じることに関してはいかがでしたか?
岡山「ほかの役に臨むときと変わりませんでした。ツチヤさんの半生が収められた作品を原作としているわけですが、僕としては何かを再現しようとは考えていなかったんです。僕が表現しようとしているツチヤ像に少なからず影響が出ると思ったので、ご本人にお会いするのはすごく緊張しましたし、お話しもなかなかできませんでした。ツチヤさんは撮影現場にも見学にいらしたのですが、やっぱりほとんどお話しできなかったですね。これまでにも僕の参加している作品の撮影現場に原作者のかたが来ることはありましたが、ツチヤさんとの距離感はまったく違うものでした。原作も映画もあくまでフィクションですが、特殊な関係性でしたね」

──脚本を読んだ印象はいかがでしたか?
岡山「準備稿の段階からたびたび読ませていただいていたのですが、撮影稿ではどこに照準が定まるのか気になっていました。ツチヤタカユキという強烈なひとりの男の人生が軸にあって、これをもって観客のみなさんに何を届けられるのか。なかなか出会うことのできないキャラクターなので、役者として演じるうえでもそうですが、本作においてこの役をどう扱うべきなのかを考えながら読んでいました。“笑い”に取り憑かれたツチヤさんの半生は、どんなふうにでも見せられるものだと思うんです。ただ、その方向性によって映画の意味合いは変わってくる。脚本を読むたびに監督とはお話をしましたね」
──岡山さんからもいろんな意見を出されたのですか?
岡山「いえ、そういうわけではありません。走り出した企画があって、あくまでも僕はいち俳優として乗せていただいたわけですから。ただ、主演を務める者として映画がどういう方向に進んでいくことになるのかはずっと気にしていました。そこでは僕も思ったことをお伝えし、作品に反映されたものもあれば、そうでないものもあります」

──脚本上のツチヤタカユキというキャラクターに対してはどのような印象を持ちましたか?
岡山「彼はお笑いの世界での夢を追いかけているわけですが、もっと本質だけを抜き取ると、ただ酸素を求めているだけなんじゃないか、とも思いました。生きるために必要な、ほかの人たちと同じように普通に呼吸ができるところへ到達するため、血が滲むような努力を重ねている。とはいえこの“努力”というものも、はたから見た第三者的な視点のもので、本人は努力だなんて思っていない。笑いを追究するために取る行動は、彼にとってすべて当たり前のことなんです。ただツチヤは、自分が欠けた存在だという感覚を持っているのではないかと感じていました。だからその欠けた部分を後天的に埋めるために必死になっている。こういった感覚はとても理解できます。俳優業とも重なる部分があるというか。彼のように本当にカオスなところに迷い込んでしまうことは、いまだってよくありますから」
──実際にどのようにしてこの役を掴んでいったのでしょうか?
岡山「はじめて原作を読んだときから、キャラクターとの距離をあまり感じませんでした。“分かる”という感覚が強くありましたから。なので、ツチヤというキャラクターに近づくための役作りみたいなことは、ほとんど意識しませんでした。根っこの部分に共感できるものを見つけたとき、それをどう表現するのか。それだけを考えていました。つまり外側から見て分かる、ツチヤの所作などです。一度はツチヤさんご本人の佇まいのようなものを演技に落とし込むべきかも考えましたが、やはりこれはフィクションを映し出す映画というメディア。結果的には脚本を基にしたオリジナルのツチヤ像を立ち上げたかたちです。僕という人間とツチヤタカユキというキャラクターが溶け合ったものを、本作が描く世界に刻めたらと。彼の視点を絶えず確保しつつ、僕としては作品の中でどう生きさせるのか、俯瞰的な視点も大切にしていました」
“役を引きずる”積み重ね

──お話を聞いていると、すごく冷静に役に臨まれた印象を受けます。でも本作でのパフォーマンスを観ていると岡山さんご本人が心配になりました。
岡山「ほかの作品と同じく、岡山天音から役(演技)に入っていくのはシームレスだったと思います。特別なスイッチがあるわけではありません。でもだからこそ、周囲のみなさんはめちゃくちゃ絡みづらかったと思いますね。カメラが回っていないところでも、ずっとツチヤのマインドだったので(笑)。周囲とのコミュニケーションを完全にシャットダウンさせていたわけではありませんが、かといってニコニコ雑談をする気にもなれない。これは本作に臨むうえでの自然な流れですね。ツチヤとして生きるための切り替えは容易ではなく、捧げるものが多かったです」
──岡山さん自身、かなり削られたのではないでしょうか?
岡山「もう自分が無くなっちゃうんじゃないかと思うくらい削られましたね。それくらい大変でした。でもだからといって、本作が特別にそうだったわけでもありません。ドラマになるものって、たとえば人の死が絡んでいることが多かったりしますよね。そこでは誰かが追い詰められていて、そのときの感情を描くことがドラマになる。これはあくまでもたとえ話ではありますが、どんな作品でも同じです。ただ本作の場合は主役としてツチヤタカユキとともに長い時間を過ごしました。あの強烈なキャラクターの原液のプールに浸かっていたので、プールから上がっても、なかなか体が乾かないというか……。そういった意味ではいつも以上に削られたかもしれません」

──役の後遺症のようなものはありませんでしたか?
岡山「もちろんあります。でもそもそも人生って、何かしらの出来事に直面するたびにその人を変えるものですよね。僕たち一人ひとりが、いろんな過去を背負ったり引きずったりしながらいまを生きている。役を演じることは、この感覚に近いものがあります。“役を引きずる”というと俳優の専売特許のようですが、誰だって強烈な体験をしたら人生が大きく変わるものではないでしょうか。ただ、俳優業とはこれの積み重ねなんです」
──ツチヤのキャラクターと俳優業との重なりのお話が出ましたが、映画はチームで作るものですよね。それでもやはり演じるのは孤独な作業なのでしょうか?
岡山「ツチヤは周囲の無理解に晒されているというよりも、彼こそが周囲に対して無理解なんですよね。だから当然、コミュニケーションは断絶されてしまう。僕個人としては、自分とは異なるいろんなタイプの人がいることを面白がるようにしています。日常生活でもそうですが、映画の現場はとくにそう。現場ごとに新しいメンバーと絆を結び、作品を生み出していきます。俳優業とは、この作業に加わることだと思います。他者を理解しようとするならば、まずはきちんと見つめることからはじまる。そうすると“無理解”という認識は生まれないと思うんです。こういったところを僕は大切にしたいと思っています。映画の中のキャラクターもそうですが、その人にはその人にしかない、僕とはまったく違う人生を歩んでいる。そこに思いを馳せることが大切なのかなと」

『笑いのカイブツ』
監督 / 滝本憲吾
脚本 / 滝本憲吾、足立紳、山口智之、成宏基
出演 / 岡山天音、片岡礼子、松本穂香、前原滉、板橋駿谷、淡梨、前田旺志郎、管勇毅、松角洋平、菅田将暉、仲野太賀
公開 / テアトル新宿ほか公開中
©2023「笑いのカイブツ」製作委員会
笑いに人生を捧げるツチヤタカユキ(岡山天音)は毎日気が狂うほどにネタを考える日々を過ごしていた。念願叶ってお笑い劇場の小屋付き作家見習いになるも、愚直で不器用なツチヤは他人には理解されず淘汰されてしまう。失望していた彼を救ったのはある芸人のラジオ番組だった。番組にネタや大喜利の回答を送るハガキ職人として再びお笑いに人生をかけていた矢先、「東京に来て一緒にお笑いやろう」と憧れの芸人からラジオ番組を通して声がかかった。そんなツチヤは東京で必死に馴染もうとするが……。
岡山天音
おかやまあまね|俳優
1994年、東京都生まれ。2009年に『中学生日記 シリーズ・転校生(1)~少年は天の音を聴く~』(NHK教育)で俳優デビュー。主な映画の出演作に『ポエトリーエンジェル』、『FUNNY BUNNY』、『キングダム』シリーズ、『あの娘は知らない』、『BLUE GIANT』(声の出演)。ドラマでは、NHK連続テレビ小説『ひよっこ』、『日曜の夜ぐらいは…』(朝日放送テレビ)、『こっち向いてよ向井くん』(日本テレビ系)など多数出演。
撮影 / 池村隆司 取材・文 / 折田侑駿 スタイリスト / 岡村春輝 ヘアメイク / 森下奈央子