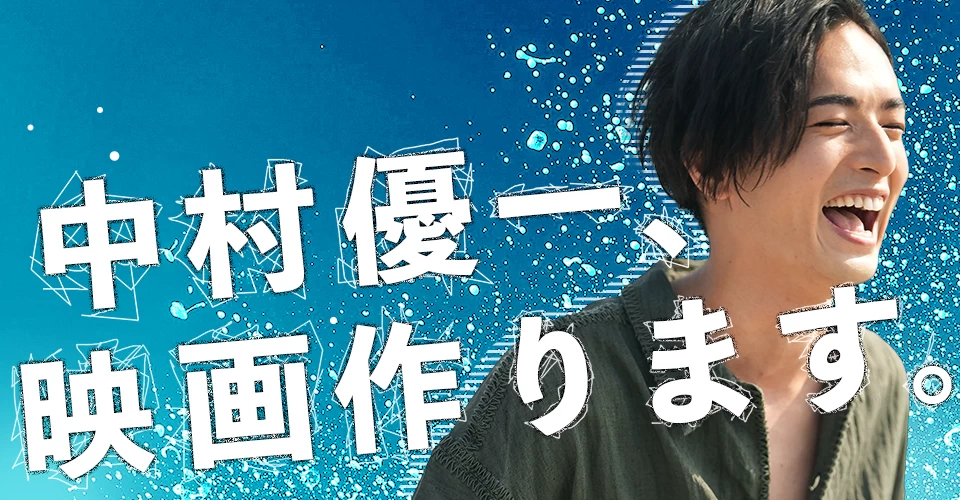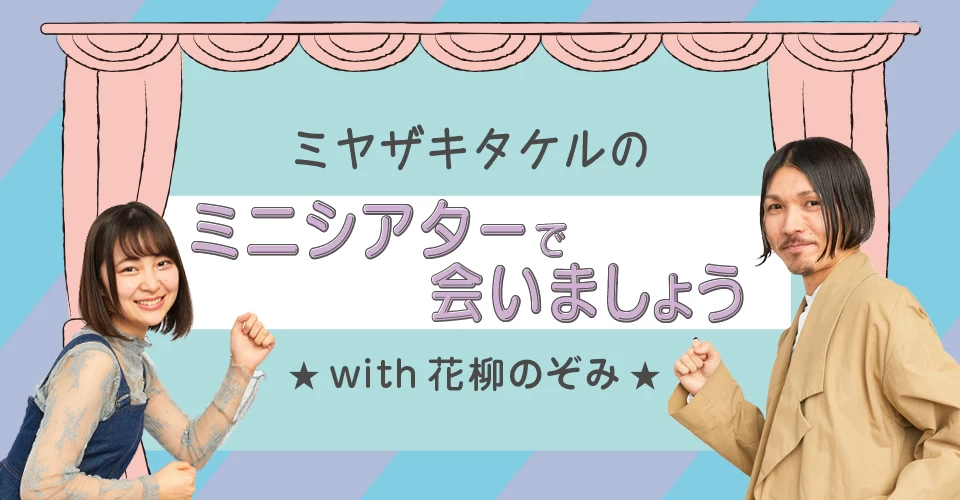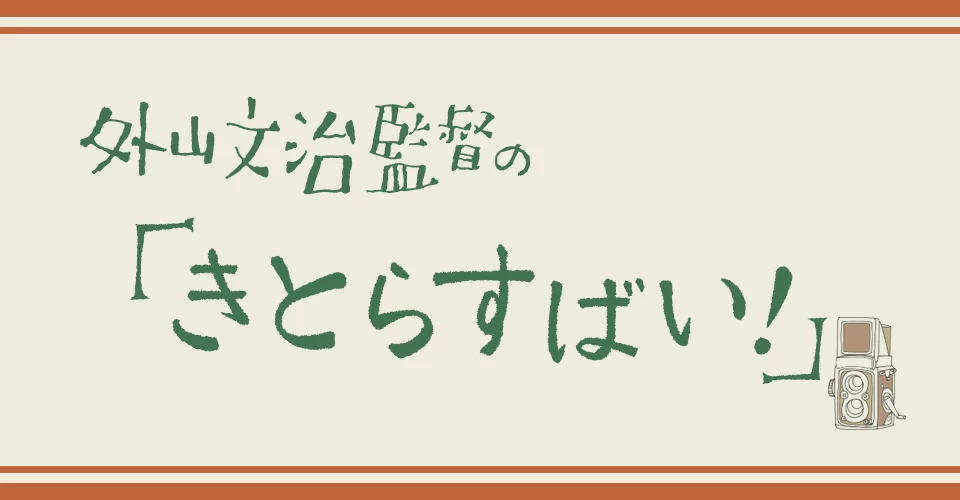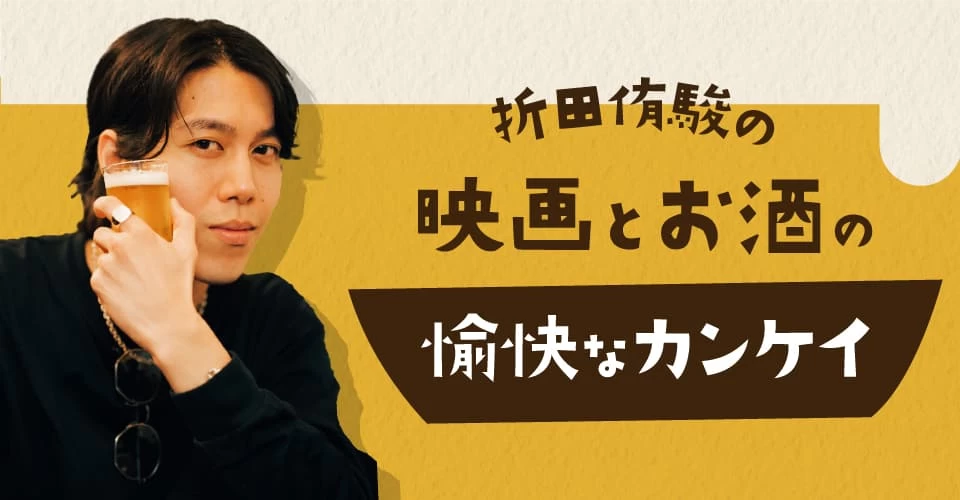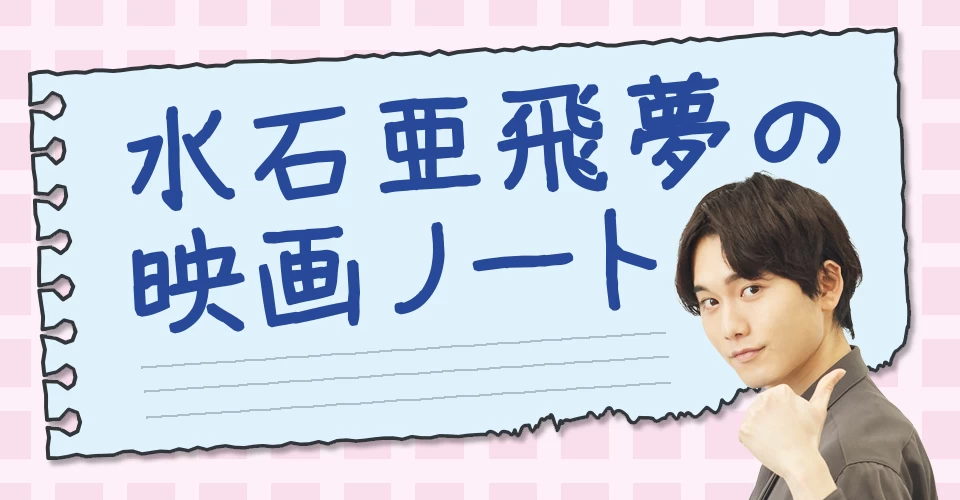タイトルを目にして劇場へ駆け込んだ『ぼけますから、よろしくお願いします』【根矢涼香のひねくれ徘徊記 第2回】 2021.11.14


ショッピングセンターというのはどの地域もだいたい似ている。明るすぎない照明、フードコートの食べ物が集まった匂いに、誰にも歩き抜かされないエスカレーター。
「楽しみにしとるけぇね」
聴こえてくる会話の音色が、初めて歩く場所だと教えてくれる。車窓から見える、山に並ぶ茶色い瓦屋根、街を挟むように反対側には海があり、海の向こうに連なるのは、薄く青みがかった島々の頭だ。初めての広島県。これまでは物語の中だった呉の街で、私はキャリーケースを引っ張っている。撮影前日、時間が許す限り町の生活に染み付いた通りや店を歩き回り、演じる人物を想像し、そこに漂う空気を吸い込み肉付けをしていく。広島といえば任侠モノや戦時中を描いた作品が思い浮かぶけれど、私には耳と心に沁みついた光景があるのです。
『ぼけますから、よろしくお願いします。』
娘である信友直子監督が、呉市に暮らす両親を記録したドキュメンタリー作品だ。
認知症となった母、耳の遠い父による「老老介護」の1200日の記録。タイトルを目にしたときは衝撃を受けた。ポスターに写るご両親の可愛らしい笑顔に導かれ、ポレポレ東中野に駆け込んだのを覚えている。監督が撮影に有したであろう勇気を、見る側の私も持つ必要があった。だって本当ならばこれは、目を背けたい、いつかは自分にも起こりうる現実だから。

生きていれば歳を取る。お腹の周りに肉はつくし、前はできたことができなくなる。政治家だろうと八百屋だろうと、時間は平等に訪れる。夢のために上京してきた私にも、私の両親にも。
広島弁で繰り広げられる親子での会話。不思議な懐かしさ。あけすけな距離。信友監督の目を借りて、父・良則さん、母・文子さんお二人の人柄溢れる声に迎えられ、よそさまのウチに“帰省”した気持ちになれる。
家族という限られたコミュニティだからこそ言える皮肉やお節介があって、それぞれに抱える苦悩がある。分かち合うことができないもどかしさに思わず胸が詰まるが、彼らの持ち前の明るさに、涙と笑いが一緒に溢れてしまうのだ。映画が終わるとき、悲しさや暗さよりも、あたたかな愛でいっぱいになった。
映画でわざわざ現実を考えたくないという人もいる。私だってため息をつきたくなる日々から目を背けたい。宣言されずとも常時緊急事態だ。「立ち止まったりしたら、歩き出すんがたいぎい」と劇中で文子さんが呟く。おそらく本人の言った意味とは違うが、実際ひとたび先々の憂いに向き合ってしまうと、これまでと同じ速度と腕の振り方で歩くことは、どうしても躊躇われる。
どれだけそばにカメラが寄っても、どれだけ近くに身体があっても、血を分けていようがパートナーだろうが、結局のところ、私たちは孤独な個人なんだと思い知らされる。いつまでも自分の力で生きていけたら良いけれど、無人島に一人ぽっちじゃない限り、人とのつながりは切り離せない。だったら大丈夫なフリなんかしないで、しんどいねえと笑いあって寄りかかっていい。
老いて忘れてゆくよりも、自分からは見えないところへの想像を欠いてしまう方がよっぽど悲しいことだ。
そう対峙させてくれるのも、映画だからこそ。どこか似ていて此処にしかいない私たち。あちらこちらの言葉で夕飯の支度をしては、同じお日様のもとで目を覚ます。次はいつ会えるだろうかと心では思っていても、仕事や目指すものを追うにつれて、いつでも帰れるからと後回しになる。場所が変われば、戦わなければいけないものも自然と変わってゆくのは当たり前だ。けれどたまには振り向きたい。これまで1日だって、一人で歩いてきた日はあるだろうか?

撮影を終え、ロケバスでホテルに戻る道。牡蠣棚の並ぶ穏やかな海が夕日に染まる。撮影を見ていたおじいちゃんおばあちゃんがくれたミカンと同じ色。港の波止場、家々に、夜空の星に代わっていくつもの明かりが灯る。「おかえり」を言っているみたいに。仕事が落ち着いたらすぐにわたしも、帰ろうと決めて、両親に電話をかけた。
 ©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会
©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会
『ぼけますから、よろしくお願いします。』
監督・撮影・語り / 信友直子
デジタル配信中
©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会
撮影 / 角戸菜摘 スタイリスト / 山川恵未 ヘアメイク / 染川敬子(TOKYO LOGIC) 編集 / 永井勇成 衣装 / ブラウス¥5,850/Wild Lily〈問い合わせ先〉Wild Lily 03-3461-4887

1994年9月5日、茨城県東茨城郡茨城町という使命とも呪いとも言える田舎町に生まれる。近作に入江悠監督『シュシュシュの娘』、野本梢監督『愛のくだらない』などがある。石を集めている。