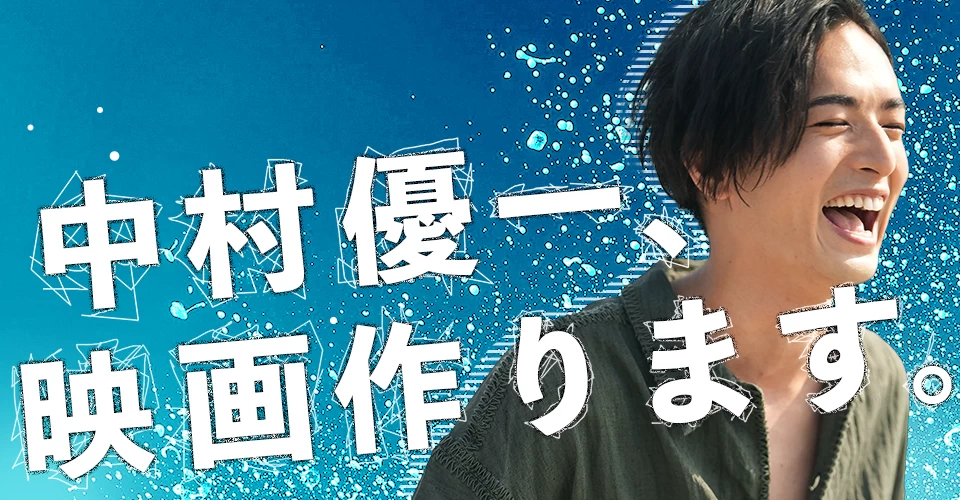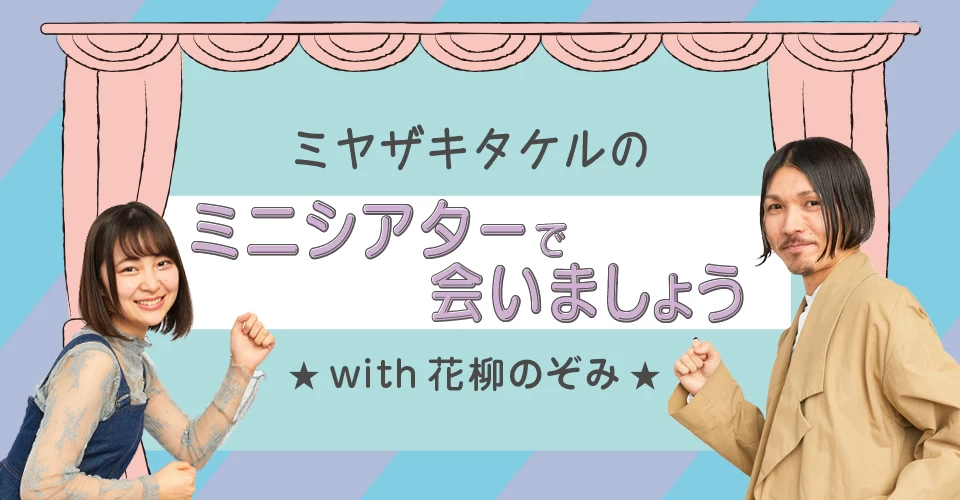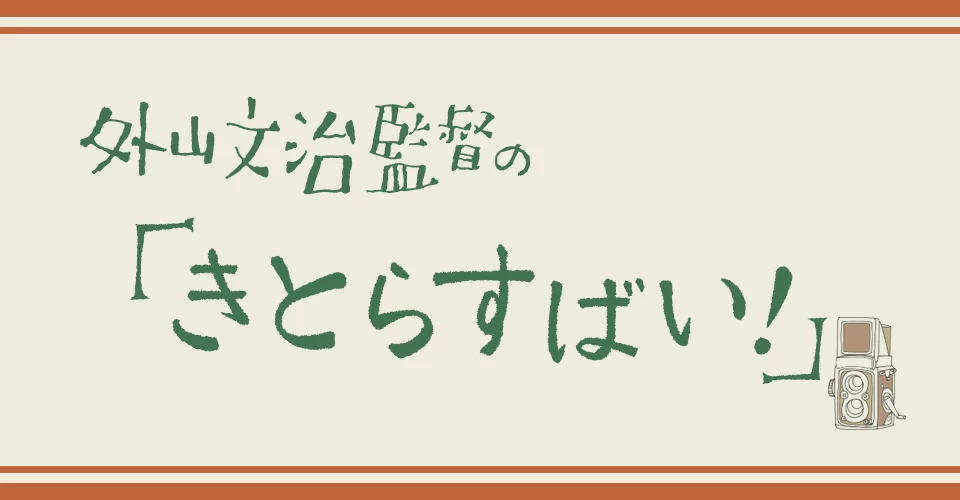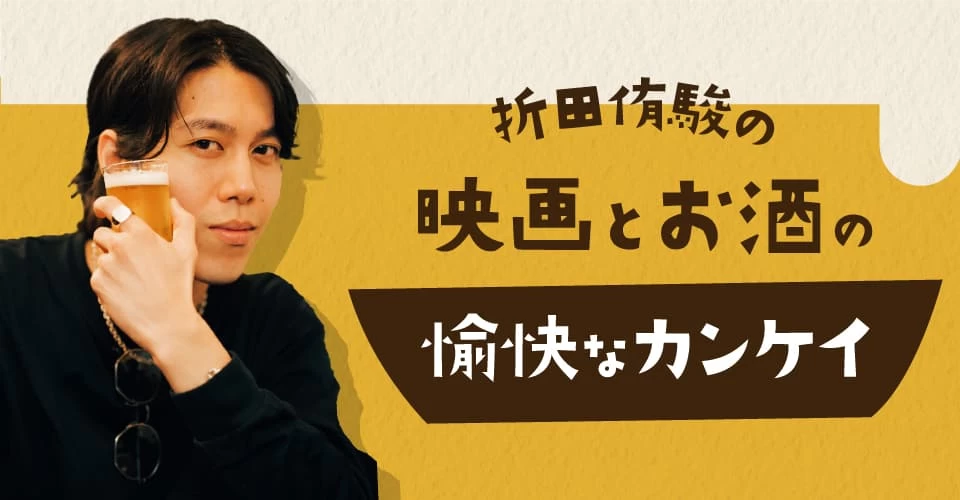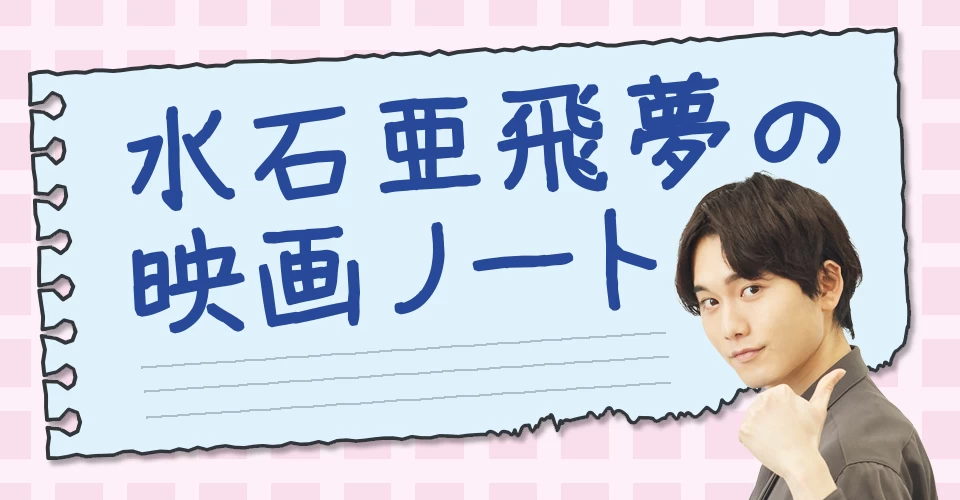岡本玲「待っている人がいることのありがたみを感じました」『茶飲友達』外山文治監督 × 岡本玲 インタビュー 2023.2.8


岡本玲を主演に迎え、外山文治監督がオリジナル脚本で手がけた最新作『茶飲友達』。高齢者の“生”と“性”に焦点を当て、世代を問わず、現代人が抱える孤独を見つめた作品だ。ワークショップ・オーディションを経て主人公・マナ役を務めた岡本と、シリアスな題材を独自の手法で映画作品に昇華させた外山監督。本作で初顔合わせとなった二人に話を聞いた。
自分自身が映画監督として果たすべきことが『茶飲友達』で定まったと感じます。──外山文治
制作前から応援してくださる人がいること、待ってくれている人がいるありがたみを改めて感じることができました。──岡本玲
このタッグ誕生の経緯

外山「岡本さんとの本格的な出会いはワークショップ・オーディション(以下、WSAD)です。667名の応募があって、彼女もその中にいました。私の前作『ソワレ』(2020年)は岡本さんの故郷・和歌山で撮っていたこともあって、観てくれていたんですよね。私は彼女が出演した舞台を観ていて、互いに面識はあった。ただ、仕事はしたことがありませんでした。なので、俳優と監督という関係性で対面したのはWSADが初めてのことでしたね」
岡本「私自身は映画が大好きなのに、俳優としてあまり映画に関わってこれなかったことがコンプレックスになっていました。そんな折、本作の企画があることを知ったんです。たとえここで出演ができなかったとしても、映画というものに自分の方から近づいていける。大きな転機になるはずだと思いました。WSADでは自己紹介もそこそこに、配布された台本を参加者みんなで演じましたが、オーディションというよりはワークショップ色が強かったです」

©2022茶飲友達フィルムパートナーズ
外山「やっぱり、15分程度のオーディションで俳優の実力や魅力のすべてを知るのは難しいです。それなりに時間をかけないと見えてこない部分を一人ひとり見たかったので、どうしても長い時間が必要でした。私自身も大変ですが、互いに高め合っていきたい思いがあります」
岡本「セリフをどう言うかということよりも、役や俳優自身の生き様をそこにどれだけ刻むことができるか。どれだけ表面的に装うことなく、その場にいられるか。演劇の稽古場でも重要視されることですが、外山さんの現場もそうでした。自分がどういう俳優なのかを見つめる時間でもありましたね」
物語の着想と、その捉え方

外山「長編デビュー作である『燦燦-さんさん-』が2013年に公開されようとしていた頃、時代に先駆けたものを世に発信できそうだという気持ちでいたんです。同作は高齢者の婚活をテーマとしていますから。でも公開一ヶ月前に、“茶飲友達、募集。”と謳って高齢者たちが売春をしていて、摘発されたニュースを知りました。このときに、映画よりも遥か先を行く世の中に打ちのめされたんです。と同時に、自分の正義感が揺らぐ経験をしました。法を犯したという意味では悪かもしれませんが、果たして孤独な高齢者たちの抱えているものはどうなるのかと。世の中は善悪二元論ですが、そこに収まらないものがある。このことを映画にしたいとずっと思っていました」

©2022茶飲友達フィルムパートナーズ
岡本「私はその事件のことを知らずに生きてきました。劇中のセリフにもありますが、お年寄りを“平和の象徴”のようなイメージでくくっていたんです。なので脚本を読んだときに事実以上に、無知で生きてきた自分に対してショックを受けました。私は自主制作で演劇を作っているのですが、次作では“傷つくことを忘れた人たち”の物語を描きたいと考えていまして、『茶飲友達』はまさにそれ。この共鳴を感じたとき、“私にしかできない”と思ったんです。マナ役に関しては、脚本を読んだだけではイメージが浮かびませんでした。どんな服装で、どんな表情で、どんな声をしているのか。彼女には人前で隠してきた苦しさがあって、でもそれは私も同じ。これらのことを外山さんには素直に伝えました」
映画作りにおける二人の印象的なやり取り

外山「マナは難しい役だと思います。彼女だけを追い続ける映画ではない中で、本作のテーマと密接な関わりを持つマナというキャラクターを表現しなければならない。マナは非常に多面的で複雑な人物です。この役を岡本さんにお願いしたうえで、彼女の演技に関して誰よりも詳しくなろうと思い、過去の出演作をほとんど見ましたね。
それを経て、岡本さん自身があまり世にさらしていない部分にヒントがあるのかもしれないという考えにたどりつきました。岡本さんに対して持っていた印象は、まず“上手い俳優”だということ。踏んできた場数も違いますからね。ただ私としては、その先のところに到達する瞬間を見たかった。例えばそれは“目が釘付けになる”みたいなことで、彼女がそのポテンシャルを持っていることは分かっていたんです。どうすればそれを引っ張り出せるのか考えていました。そもそも岡本さんがこの企画に参加するのって相当な覚悟ですよね。出演できるか分からないわけですし。クリエーションの過程で彼女がマナという役を自分のものにしていく姿は凄いものでしたし、それは俳優業を天職とする彼女の凄みとして画面に刻まれていると思います。“上手い”のではなく、“凄い”んです」

©2022茶飲友達フィルムパートナーズ
岡本「マナは誰かを傷つけたくないし自分も傷つきたくない。だったら、その場その場における最善のマナの姿でいればいいのかなと。それが分かったとき、彼女を演じる苦しさは無くなりました。撮影前に外山さんから“声に芯がありすぎるから、もっと高い声でやってください”と言われたのが印象に残っています。私自身、演じる際に使うのが嫌な声があるのですが、外山さんからはそれを求められました。いま発しているこの声です。この届くかどうか分からない不安定な声を使うのは、普段の自分をそのまま扱うということです。でも、これを演技に持ち込むことができた瞬間から、セリフの言い方を考えたりすることは無くなりました」
本作を経て思うこと

岡本「コロナの影響で撮影が延期になりましたが、だからこそ、撮影までの期間に俳優同士で特別な関係性を築くことができたように思います。みんな肩の力を抜いた状態で密なコミュニケーションを取り合って、何でも意見を言い合いました。何の不安もない状態でカメラの前に立てましたし、それは完成した映画の画に表れていると思います」
外山「本作のテーマが“孤独とどう向き合うか”というものなので、誰もが孤独感を増しているこの環境下、必要な映画になっているのではないかと思います。本作を撮ると決めた際、関わってくださる誰かにとって、心の拠り所になればいいなと考えていたんです」

岡本「“家族”が一つのテーマである作品に、自分自身のパーソナルな部分を持ち込んで挑めたことで……大人になりました(笑)。いままでは自分がまだ子どもであったことを受け入れたというか。一人の人間として、違うフェーズに入ることができた気がしています。これからの俳優人生でターニングポイントになった作品を挙げていく機会があると思うのですが、『茶飲友達』はまさにその一本ではないかと。クラウドファンディングも実施したので、制作前から応援してくださる人がいること、待ってくれている人がいるありがたみを改めて感じることができました。受け取る相手がいてこそモノ作りは成立しますよね」
外山「私は演出家として、目の前にいる俳優のそれまで見たことのなかった表情を、世の中に向けてどう引き出していくかを考えることに生きがいを感じています。彼ら彼女らをどう輝かせるか。本作ではそれを40人近くの俳優に対して実践しました。これこそが自分の好きなことなのだとよくよく分かりましたし、これからもこれを続けていくのだという指針になりました。自分自身が映画監督として果たすべきことが『茶飲友達』で定まったと感じています」

外山文治
そとやまぶんじ|映画監督
1980年9月25日、福岡県生まれ宮崎県育ち。長編映画監督デビュー作『燦燦ーさんさんー』で「モントリオール世界映画祭2014」より正式招待を受ける。2020年、豊原功補、小泉今日子によるプロデュース映画『ソワレ』を公開。「第25回釜山国際映画祭」【アジア映画の窓】部門に正式出品される。
岡本玲
おかもとれい|女優
1991年6月18日生まれ、和歌山県出身。 第7回雑誌「ニコラ」専属モデルオーディションを獲得し、デビュー。以後、ドラマ・映画・CM・舞台と多方面で活躍中。代表作にNHK 連続テレビ小説「純と愛」、「わろてんか」や映画『弥生、三月‒君を愛した30年』、舞台「森 フォレ」、「湊横濱荒狗挽歌〜新粧、三人吉三。」、「陰陽師 生成り姫」、『ロビー・ヒーロー』、「レオポルトシュタット」など。また、4月1日から出演舞台「ブレイキング・ザ・コード」(シアタートラム)が上演予定。

『茶飲友達』
監督・脚本 / 外山文治
出演 / 岡本玲、磯西真喜、海沼美羽 / 渡辺哲
公開 / 2月4日よりユーロスペース 他
©2022茶飲友達フィルムパートナーズ
あらすじ
妻に先立たれ孤独に暮らす男、時岡茂雄がある日ふと目にしたのは、新聞の三行広告に小さく書かれた「茶飲友達、募集」の文字。その正体は、高齢者専門の売春クラブ「茶飲友達(ティー・フレンド)」だった。運営するのは、代表の佐々木マナ とごく普通の若者たち。彼らは65歳以上の「ティー・ガールズ」と名付けられたコールガールたちに仕事を斡旋し、ホテルへの送迎と集金を繰り返すビジネスを行なっていた。マナはともに働くティー・ガールズや若者たちを “ファミリー”と呼び、それぞれ孤独や寂しさを抱えて生きる彼らにとって大事な存在となっていた。ある日、一本の電話が鳴る。それは高齢者施設に住む老人から「茶飲友達が欲しい」という救いを求める連絡であったー。
撮影 / 角戸菜摘 取材・文 / 折田侑駿 スタイリスト / 森宗大輔 ヘアメイク / SHIZUE