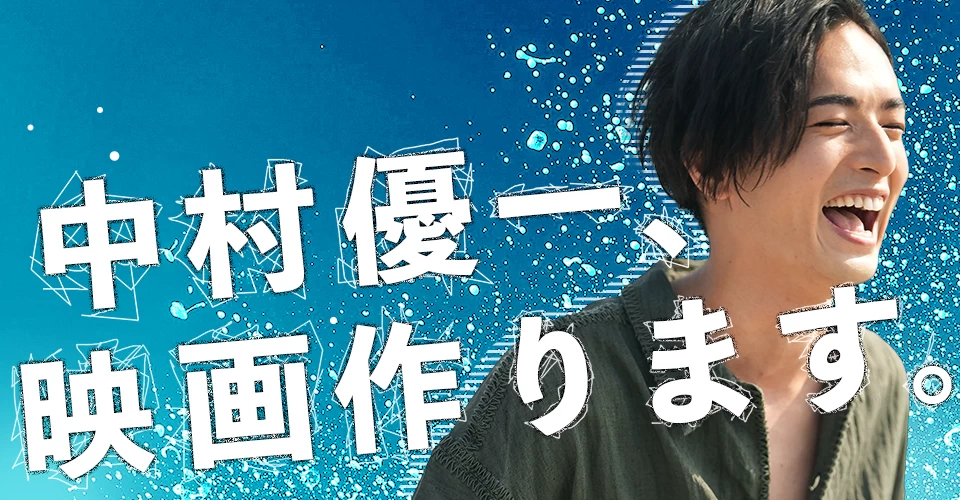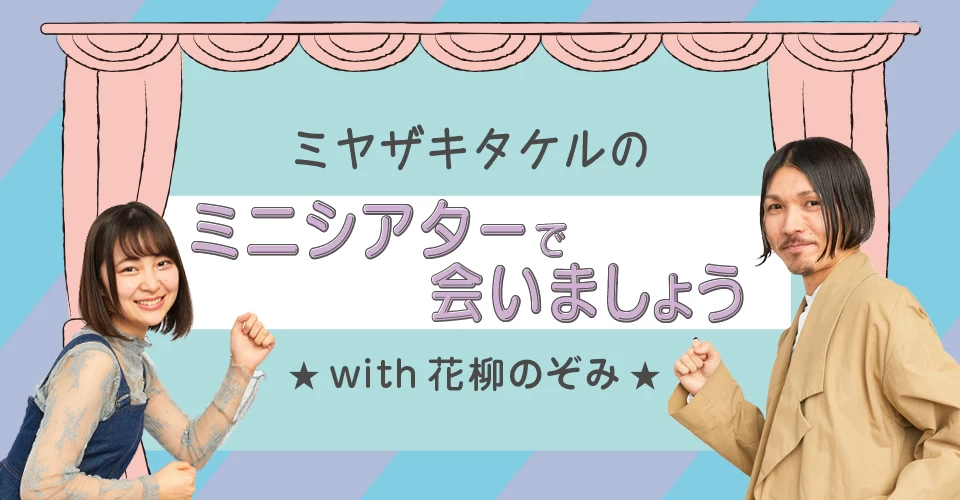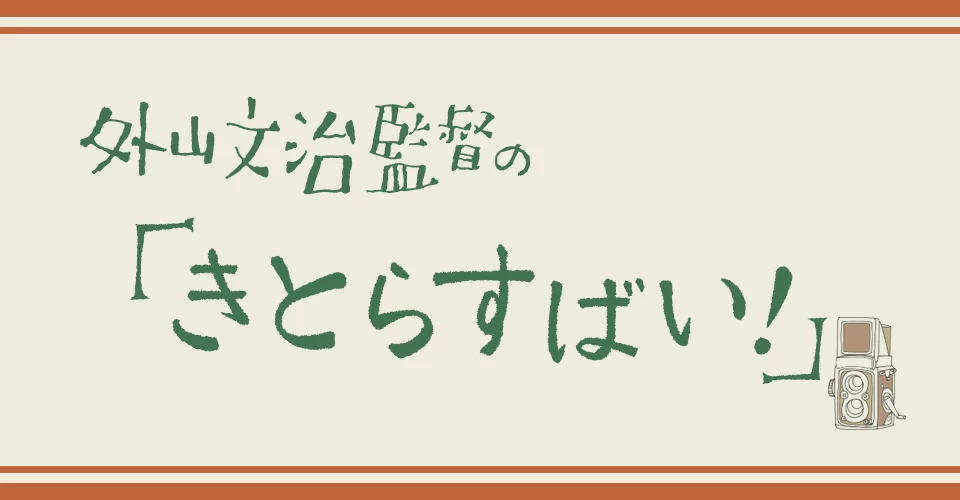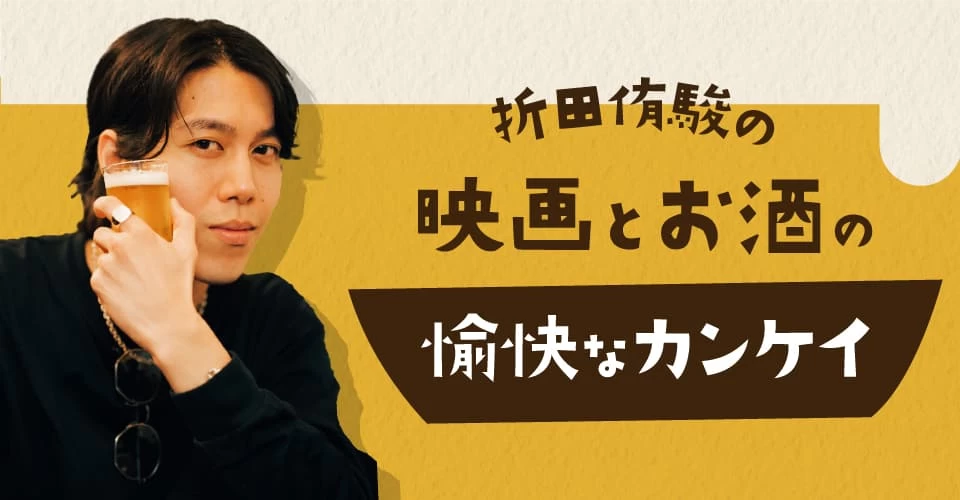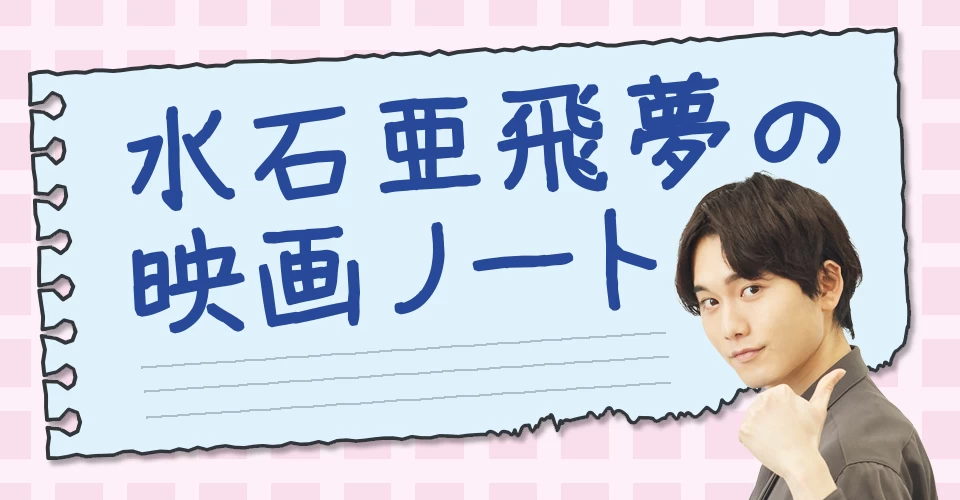毎熊克哉×串田壮史監督 対談後編 - 『初級演技レッスン』で映画初タッグ 2025.4.4


俳優・毎熊克哉による連載企画「毎熊克哉 映画と、出会い」では、前回に引き続き、『初級演技レッスン』の串田壮史監督とのお話をお届け。彼が主演を務める本作は、謎めいたアクティングコーチの蝶野穂積(毎熊)が即興演技をとおして受講者たちの記憶に入り込み、その人生を遡っていくことで奇跡に巡り合うさまを描いたもの。
この「後編」では、串田作品の魅力を対話の中で深掘りしていく。果たしてそこから何が見えてくるだろうか──。
俳優・毎熊克哉が思う、串田作品の魅力
──毎熊さんは串田監督が生み出す独特の世界観に魅せられたとおっしゃっていましたが、これについてもう少しお聞きしたいです。
毎熊:串田さんの作品の魅力について語るときに必ず出てくる言葉は“緻密さ”です。前回もお話ししたように、緻密さと監督の強いこだわりによって串田作品は成立しています。これまでいろんな映画を観ては感動してきましたが、『写真の女』を観たときに、なんだか「完璧だ」と思ったんですよ。あのときの感覚を言語化するのは難しいのですが、一つひとつの画の構図が素晴らしかったし、最初から最後まで一度も緊張感が途切れることなく見入ってしまったんです。
──一瞬たりとも見逃してはならない感じが、串田さんの作品には冒頭からありますよね。
毎熊:まさにそうなんです。長編第2作目である『マイマザーズアイズ』もそうですが、よく分からないカットも、映画の流れをたどっていくうちに、絶対に必要だったのだと気づかされます。『写真の女』も『マイマザーズアイズ』も、決して分かりやすい映画ではありません。それと同時に、「映画」というフォーマットでしか表現できないことを実践されています。いち観客としてではなく、ひとりの俳優として、串田監督が生み出す世界に入りたいと思っていました。

──串田監督は「演技のことは演技のプロにお任せします」というスタンスでこの現場に臨まれていたと聞きました。このスタンスはずっとなのですか?
串田:そうです。なぜそうなったのかというと、これは僕が編集も自分でやっていることが大きく関係しています。たとえばですが、編集の段階で映像素材を「テイク1」から順に見ていきますよね。すると、テイクを重ねるごとに演技が説明的なものになっていくことに気がつきます。そうしてけっきょく、「テイク1」を使うことが僕の場合は多い。撮影前に伝えたことを、役者さんが表現しようとしてしまうからだと思います。説明的な演技というのは、作品を説教くさいものにしてしまう恐れがあると僕は考えています。それだとお客さんも楽しくないんじゃないのかと。
毎熊:僕自身も余白のある柔軟な現場が好きですし、前編でもお話ししたように、この作品に関わるひとりの役者として、串田さんが欲するものを汲み取ろうと努めていました。
串田:撮影現場でいったい何が起こるのかを楽しみにしているタイプなので、あまり事前に固めてしまうと面白くないでしょうね。僕は撮影現場でも、編集室で素材を見ている感覚で立っていますね。
全編アフレコにする真意
──串田監督の作品の特徴のひとつとして、音声がすべてアフレコだというのがありますよね。なぜ全編にわたってアフレコなのでしょうか?
串田:アフレコを採用していることについては、技術面と芸術面の、大きくふたつの理由があります。まず技術面に関していうと、音はすべてアフレコなので、撮影現場で“音待ち”をする必要がないんです。そもそも僕の作品の現場には録音部がいませんからね。『初級演技レッスン』の現場で印象に残っているのは、インテリアショップのシーンを撮影しているときのことです。あれは実際に営業をしているお店だったので、店内BGMが流れていました。これがもしも同録の場合、編集段階でそのBGMを消す必要が出てきます。でも、登場人物たちはこのBGMを耳にしていたはずですよね。つまりある観点から見ると、同録のほうが不自然なんですよ。本番でカメラを回す際、周囲の人々は静かにしていなければなりませんしね。ですが僕の作品の現場では、車の走る音がどれだけうるさくても撮影を続けられます。僕たちは通常、そういったさまざまな音に囲まれた環境の中でコミュニケーションを取っているわけですから、本当はこちらのほうが演技をするうえでリアルな状況を作れるはずなんです。
 © 2024埼玉県/SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ
© 2024埼玉県/SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ
──作品が持つ世界観に不必要な音を、現場で排除する必要がないわけですね。いままで考えたことがありませんでしたが、とても理に適っている手法なのだと思います。
串田:ここまでは現場における技術面の話で、あとは編集における芸術面ですね。これに関しては、あとから加える音によって、表現の幅が広がるんですよ。たとえば、登場人物の心臓の高鳴りや特定のシーンにおける印象的な音など、自由自在に加えることができます。ノイジーな音を重ねれば、なんだかザワザワしたシーンに仕立てることもできますから。なので現場の段階ですでに、サウンドデザインについても考えをめぐらせながら撮影を進めているんです。
毎熊:同録には同録の強さがあると思うのですが、アフレコにはアフレコの強さがあるのを実感しましたね。映画に必要な音をあとから作り出すという発想も面白いですし。同録だと現場でしか絶対に生まれることのない音を収められるいっぽう、アフレコだったらセリフに関しても何度でも録り直しができます。役者をやっていると、完成した作品の自分のセリフの言い方に対して、「別のニュアンスがよかったかもな」と思うことが多々あるんですよ。クランクアップ後にレコーディング室に行くのは、いいことなんじゃないかと思いますね。作品をよりよくするために。

──アフレコでは映像を見ながら声だけで演じるわけですよね。そこにはまた特別な難しさがあるのではないですか?
毎熊:人それぞれに得意なやり方があると思うのですが、僕は映像に合わせてやるのがすごく苦手です。モニターに映る自分の口元に合わせてセリフを言うのだと、タイミングばかり気にしてしまうんですよ。なのでアフレコの際は役の感情どうこうよりも、ある種の音楽的なノリを重視して臨んでいます。
串田:現場での僕は役者さんに対してあまり指示を出しませんが、アフレコの際には言いますね。声の高さや低さだったり、セリフのスピード感だったり。声にこそ、人間の感情やキャラクターというものが、もっとも表れると思っています。

──いち観客として魅せられた串田監督の作品世界に入ってみて、毎熊さんは改めていかがでしたか?
毎熊:『初級演技レッスン』の脚本は、読んだだけではよく分かりませんでした。読み物として面白い脚本が、いい映画になるわけではないことを僕は知っているつもりです。素晴らしいシーンだと思っていたのに、いざ映像になってみると、そうでもないと感じることがこれまでにも多々ありました。ですが、カメラの前に立っていて肌で感動を味わえたとき、それはやはり完成したシーンも素晴らしいものになっているものです。カメラの前には、役者だけが感じ取ることのできる、うまく言語化できない“何か”があったりするものなんです。串田さんの描く世界は、カメラをとおしてこそようやく見えてくる。「これぞ映画だ」と改めて思いました。
串田:ありがとうございます。次は、王道のホラーか、ヒューマンドラマを撮りたいと考えています。『初級演技レッスン』が世に出ることで、どちらにもいけるような気がしているんです。そしてヒューマンドラマなら、コメディ寄りのものがいいですね。コメディ作品って、主人公をどれだけ大変な目に遭わせられるかが重要だと思っているので、サディスティックな妄想が膨らみます(笑)。
串田壮史
くしだたけし|監督
1982年生まれ、大阪府出身。ピラミッドフィルム所属。
長編デビュー作『写真の女』(20)は、世界中の映画祭で40冠を達成し、7カ国でのリリースが決定。同作でSKIPシティアワードを受賞して製作された『マイマザーズアイズ』(23)は、イギリス最大のホラー映画祭・ロンドン フライトフェストで《Jホラー第3波の幕開け》と評され、世界に向けて配給が行われている。
毎熊克哉
まいぐまかつや|俳優
1987年3月28日生まれ、広島県出身。2016年公開の初主演映画『ケンとカズ』で第71回映画コンクールスポニチグランプリ新人賞、第31回高崎映画祭新人賞を受賞。公開待機作に『無名の人生』、『時には懺悔を』、『桐島です』が控えている。

『初級演技レッスン』
2025年2月22日(土)より、渋谷ユーロスペース、MOVIX川口ほか全国順次公開
毎熊克哉
大西礼芳 岩田奏
鯉沼トキ 森啓一朗 柾賢志 永井秀樹
監督・脚本・編集:串田壮史
制作プロダクション:Ippo/デジタルSKIPステーション
製作:埼玉県/SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ
配給:インターフィルム
© 2024埼玉県/SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ
撮影:西村満 取材・文:折田侑駿

1987年3月28日生まれ、広島県出身。2016年公開の主演映画『ケンとカズ』で第71回毎日映画コンクール、スポニチグランプリ新人賞など数多くの映画賞を受賞。以降、テレビ、映画、舞台と幅広く活躍。主な映画出演作に『孤狼の血 LEVEL2』『マイ・ダディ』(21)、『猫は逃げた』『冬薔薇』(22)、『世界の終わりから』(23)、『初級演技レッスン』『悪い夏』『「桐島です」』(25)等。公開待機作に『安楽死特区』『時には懺悔を』が控えている。