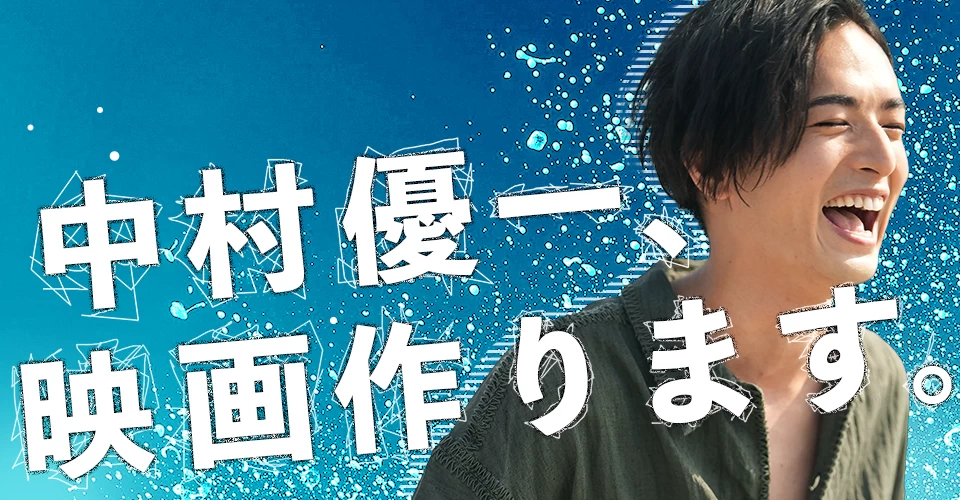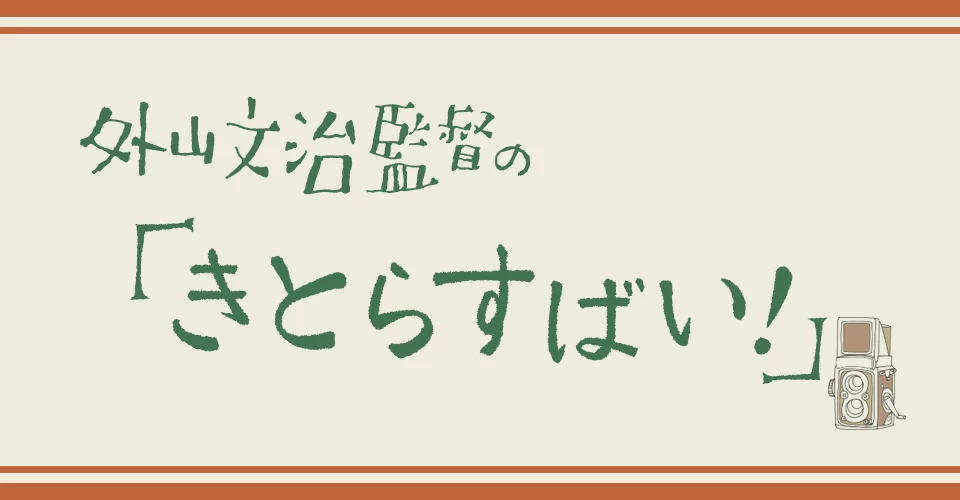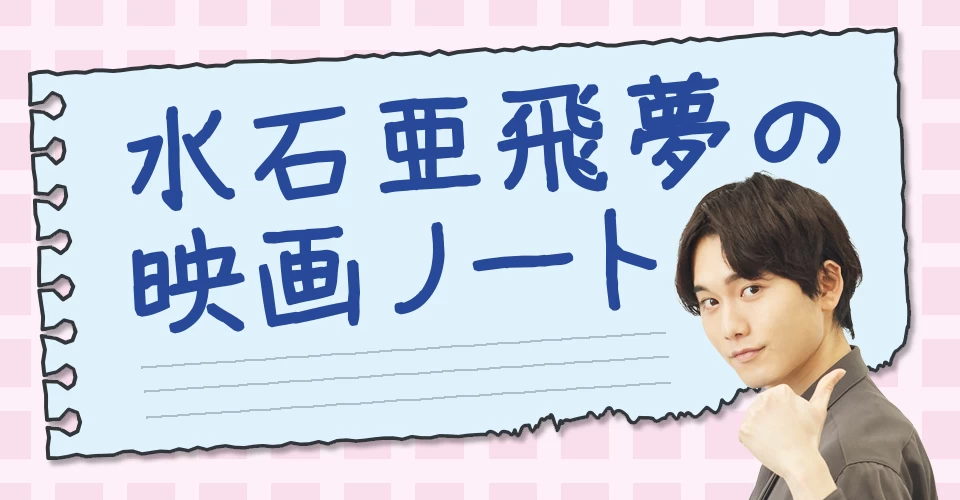毎熊克哉×山中瑶子監督 対談後編 - 葛藤と緊張 2025.10.3


俳優・毎熊克哉による連載「毎熊克哉 映画と、出会い」では前回に引き続き、『あみこ』や『ナミビアの砂漠』などの山中瑶子監督がゲストとしてご登場。
この「後編」では、毎熊の主演作である『「桐島です」』の話にはじまり、仕事であるのと同時に表現活動でもある映画づくりにおいて、ふたりの抱える葛藤などについても語っている。大きな期待をかけられる俳優と監督は、それぞれ何を思っているのか──。
自分が自分のことを信頼できるかどうかが基準なんですよね──山中瑶子
自分ごときがどこまでジャンプできるのか。その挑戦の繰り返しなんです──毎熊克哉
──「前編」では『ナミビアの砂漠』を入口に、監督と俳優というそれぞれの立場から、映画づくりに臨む際のスタイルやスタンスについてお話しいただきました。この「後編」で山中さんは、毎熊さんの作品選びについてお聞きしたいんですよね?
山中:『「桐島です」』を観て、主人公にシンパシーを感じました。こうして生きていると、この社会に対して容認できないことや嫌なことがたくさんあります。私自身、すごく偏ったタイプの人間だと自覚してもいます。でも映画だからといって、自分と異なる価値観や考え方を持った人々を排するわけにもいかない。毎熊さんはそれぞれの作品や役とどう関係し合っているのかなって。

毎熊:主人公の桐島は世の中的にはテロリストです。映画は彼の人生を肯定するようなところがあるので、果たしてどんな反応が生まれるか、不安がなかったわけではありません。でもこれは史実を基にしているとはいえ、あくまでも映画ですし、監督はあの高橋伴明さんです。声をかけてもらえたのなら、僕はもちろん参加します。映画づくりって、監督たちがどう作品に向き合おうとしているのかが重要だと思うんです。作品選びのようなものはご縁があってこそ。監督たちの想いに共鳴して参加を決断することが多いですね。
山中:いただいたお話のすべてに応えていた時期はありますか?
毎熊:なんでもやっていた時期がありますよ。仕事がなかった期間が長いので、「なんでもやる」という気持ちはいまも変わらずあります。でも僕の身体はひとつしかない。仕事をいただけるのは本当にありがたいことなのですが、どうしてもお断りしなくちゃならない場合が出てきてしまいますね。
山中:私はもともとそんなにやりたいことがあるタイプじゃないのですが、やりたくないことはいっぱいあるんです。でも仕事なので、そんなことは言ってられません。思考パターンが極端なので、我慢するか、跳ね除けるかしかないと思っていた時期がありました。だけどそれが少しずつ変わってきていて。私の遠くにあると思っていたものが意外と自分に合っていたり、嫌だと思っていたものが、じつはそうでもなかったり。もちろん、もっと苦手になるものもあるんですけどね。
毎熊:それは役者も同じですね。苦手だと思い込んでいたものをやってみたら、思いのほか気持ちが乗ったり、新しい自分を発見する機会になったり。それはいまでもよくありますよ。それに僕はひとりの役者として、できるだけ自分の遠くにあるものを演じていきたい気持ちがあるんです。

──この連載でいつも言っていることですね。
山中:やっぱり年齢や経験を重ねることで物事の見え方は変わってきますね。いまの私と5年前の私はまったく違う。いまは年齢を重ねていくことがすごく楽しいです。でも自分の新しい一面を発見できるいっぽうで、本質的にやるべきことや本当に好きなものから、どんどん遠ざかってしまう不安はありませんか?
毎熊:ありますね。乗り越えた壁の数だけ、そういう不安はどうしても芽生えてきてしまいます。
山中:不安を感じているうちはまだいいと思うのですが、たとえば何十年も過ごして、ふと、「あれ、いつの間にかどっかに置いてきちゃったな」みたいなことになるのが怖いんです。苦手だと思っていたものと付き合えるようになった。すると、この苦手だと思っていたものに情が湧くようにもなる。なんでも柔軟に対応できるのは素晴らしいですが、それによって見えなくなるものも間違いなくあるはず。情が湧いているがゆえに、目の前にある問題を曖昧なまま放棄してしまったり。もっとバランスよく歩けたらいいのですが。
毎熊:山中さんが言っていること、すごく分かる気がします。だから定期的に立ち止まったり、進むべき方向についてちょっと考えてみる必要があると思う。コロナで仕事が止まった期間が、僕にとってはまさにそういう時期でした。
山中:私も、5年前にコロナで現場が止まっていなかったら、あの頃の考え方のまま仕事を続けた果てに限界が来て、映画を撮るのはもうやめてしまっていたかもしれません。

──おふたりともいろんな葛藤を抱えながら作品と向き合っているとのことですが、プレッシャーに関してはどうでしょう。『ナミビアの砂漠』の誕生によって山中さんに期待をかける人は多くいますし、毎熊さんの背中を追って走り続けている俳優さんたちもいると思うんです。
山中:私はあんまり感じていないですね。というのも、幼い頃に感じていたプレッシャーがいまの私を形成しているので、大人になってから受けるプレッシャーは、もはやそこまで影響しないんです。でも緊張はしますよ。心配性でもあるので、気を抜くとつい身体が力んでしまいがち。意識的に緩めています。
毎熊:え、今日はどうですか?
山中:今日も緊張しています。
毎熊:こうしてお話しをしていて、あまりそうは感じませんでした。
山中:全然してますよ(笑)。「いつも自然体だよね」とよく言われるのですが、そんなことはありません。身体はわりとつねに緊張状態にある気がしています。だから意識的にほぐすんです。幼少期からもともとそういう性質なので、自分なりにこの世の中をサバイブしていくために対処法を身につけたんだと思います。そうそう、これもまた『「桐島です」』の主人公にシンパシーを感じるポイントです。彼は厳しい緊張を強いられながら、生きのびるための環境を見つけては溶け込んでいくわけじゃないですか。
毎熊:なるほど。たしかに。
山中:現場で緊張することがあっても、子どもの頃の緊張状態を身体が覚えているから、自然と対処しているんだと思います。監督の仕事は年に何本もあるわけではないので、現場のたびに初心に戻っちゃうんですよね。でももうプレッシャーはほとんどないかな。
──毎熊さんはどうですか?
毎熊:どうなんでしょうね。「おれなんかにそんなに興味ないでしょう」と基本的に思っていて(笑)。素晴らしい俳優は本当にたくさんいるわけで、自分に対する期待感のようなものはそんなに意識していないですね。でも、プレッシャーはすごく大切だと思っています。なのでむしろ自分で自分に負荷をかけるようにしていますね。
山中:たとえばどんな負荷のかけ方をするんですか?
毎熊:漠然とではありますが、演じる役ごとに表現のレベルの設定とか。自分で自分にプレッシャーをかけて、負荷が生まれて、緊張が生じて、筋肉の強張りや心臓の動きが早まっているのを感じる。それをひとつずつ解いていくんです。
山中:毎熊さんが現場に臨む際の方法論ですね。
毎熊:人生レベルの話をすれば、もう十分に幸せだと思うんですよ。衣食住に恵まれていて、命の危機を感じているわけでもない。これ以上、何を望むんだっていう。だから僕にとって映画の現場で役者として高みを目指すのは、こうして生きている中での探究心からくるものなのかもしれません。この活動の中で、自分ごときがどこまでジャンプできるのか。その挑戦の繰り返しなんです。
山中:けっこう感覚としては近いかもしれない。周囲からの期待感やプレッシャーではなく、自分が自分のことを信頼できるかどうかが基準なんですよね。だから自分自身の信頼を欠いてまで世間的に評価される映画をつくったとしても、とうの私自身はあんまり嬉しくない。プレッシャーをほとんど感じないのは、こういうことなんだと思います。他人に期待するよりも、みんなそれぞれに自分のことをやろうよって思っていますしね。

山中 瑶子
やまなか ようこ|監督
1997年、長野県生まれ。映画監督。初監督作品『あみこ』がPFFアワード2017にて観客賞を受賞し、多数の海外映画祭でも上映。2024年公開の『ナミビアの砂漠』は第77回カンヌ国際映画祭監督週間に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞した。文芸誌『群像』にて連載中。
毎熊克哉
まいぐまかつや|俳優
1987年3月28日生まれ、広島県出身。2016年公開の主演映画『ケンとカズ』で第71回毎日映画コンクール、スポニチグランプリ新人賞など数多くの映画賞を受賞。以降、テレビ、映画、舞台と幅広く活躍。主な映画出演作に『孤狼の血 LEVEL2』『マイ・ダディ』(21)、『猫は逃げた』『冬薔薇』(22)、『世界の終わりから』(23)、『初級演技レッスン』『悪い夏』『「桐島です」』(25)等。公開待機作に『安楽死特区』『時には懺悔を』が控えている。
撮影:西村 満
取材・文:折田侑駿

1987年3月28日生まれ、広島県出身。2016年公開の主演映画『ケンとカズ』で第71回毎日映画コンクール、スポニチグランプリ新人賞など数多くの映画賞を受賞。以降、テレビ、映画、舞台と幅広く活躍。主な映画出演作に『孤狼の血 LEVEL2』『マイ・ダディ』(21)、『猫は逃げた』『冬薔薇』(22)、『世界の終わりから』(23)、『初級演技レッスン』『悪い夏』『「桐島です」』(25)等。公開待機作に『安楽死特区』『時には懺悔を』が控えている。